このページは、既存記事「児童票の基本(目的・構成・年齢別ポイント)」を前提に、AIで児童票の”下書き”を作る具体手順をまとめた実践ガイドです。基礎の確認は先にハブ記事をご覧ください。
この記事でわかること
- 観察メモの4観点テンプレ(AIの精度を上げる入力設計)
- 年齢別のプロンプト雛形と短文例文(0–2歳/3–5歳)
- 園内データ連携で”ほぼ自動化”する実務フロー
- NG→OK言い換え辞書(主観→事実へ)
- 個人情報・同意の運用ポイント

1. まずは観察の”型”を揃える:AIは無からは書けない
AIに渡す材料(観察メモ)が事実ベースで構造化されているほど、短時間で筋の通った下書きが返ります。次の4観点でメモを集めましょう。
| 観点 | 記録のコツ | 例 |
|---|---|---|
| 出来事(エピソード) | いつ/どこで/誰と/何を/どれくらい | 11/1 朝の自由遊び、積み木に10分集中。Aくんへ自分から声かけ。 |
| 発達・生活 | 回数・所要時間・割合 | 午睡60分で安定。スプーン自立7割。 |
| 人との関わり | やり取りの具体と結果 | 交代ルールを理解、順番待ちに成功(保育士の合図なし)。 |
| 興味・関心 | 選択傾向・継続性 | 乗り物・積み木を自分で選択。青色を手に取りやすい。 |
ポイント:「すごく」「とても」などの主観語は避け、行動+回数・時間で書く。
基礎の考え方や年齢別の観点は、ハブ記事「児童票の基本」でもう少し詳しく整理しています。
2. 年齢別プロンプト雛形(コピペOK)
括弧内を観察メモに置き換えて、そのままAIに貼り付けてください。出力トーンは「客観・簡潔・保護者にも伝わる言葉」で。
2-1. 0–2歳向け
あなたは保育士です。以下の観察メモを、児童票の下書きに整えます。
- 目的:生活リズム/運動発達/情緒/人との関わりを事実ベースで記述
- 文体:客観・簡潔。推測や評価語は避ける
- 体裁:①生活・健康 ②運動・感情 ③人との関わり ④興味
- 禁則:診断名・ラベリング・過度な主観・個人名のフル表記
観察:
{出来事:…}
{発達・生活:…}
{人との関わり:…}
{興味・関心:…}
{保護者共有事項:…}
0–2歳 短文例
- 生活・健康:午睡は60分で安定。食事はスプーン使用が増え、こぼしが減少。
- 運動・感情:つかまり立ちの回数が増え、好きな玩具に手を伸ばし笑顔が見られた。
- 人との関わり:呼びかけに振り向き、同年齢児の近くで模倣遊びを行う。
- 興味:音の出る玩具と布絵本を自分で選ぶ場面が多い。
2-2. 3–5歳向け
あなたは保育士です。以下の観察メモから、児童票(就学移行も意識)の下書きを作成します。
- 視点:自己表現/認知・言語/社会性/挑戦と粘り
- 構成:事実→意味づけ→次の関わり
- 文体:客観・簡潔。評価語や断定は避ける
- 禁則:ラベリング・診断的表現・個人名のフル表記
観察:
{出来事:…}
{発達・言語:…}
{人との関わり:…}
{興味・挑戦:…}
{配慮事項:…}
3–5歳 短文例
- 自己表現:制作で「海の街」を発案し、材料・色を自分で選択。
- 認知・言語:形の分類や数の数え直しを繰り返し、5個まで正確に数唱。
- 社会性:ルール遊びで順番を守り、待ち時間に別の遊びで気持ちを切り替えられた。
- 次の関わり:制作前に材料の選び方を一緒に確認し、完成イメージを言葉にする場面を増やす。
年齢別の観点整理は、くわしくは「年齢別の例(ハブ記事内)」も参照ください。
3. データ連携で”ほぼ自動化”する実務フロー
- 記録取り込み:登降園、午睡、食事、活動記録、週案、連絡帳のCSV/APIを取得
- 前処理:日時正規化/児童ID結合/重複排除
- AI下書き:上記プロンプトに観察要約を差し込み自動生成
- 人の確認:保育士が主観語→事実表現へ言い換え、園の文体に統一
- 共有:園ルールに沿ってPDF/アプリ配布、対応ログを保存

4. NG→OK 言い換え辞書(抜粋)
- NG:落ち着きがない → OK:活動中に席を離れる場面が3回。いずれも声かけで着席に戻れた。
- NG:すぐ泣く → OK:転倒後に涙が出たが、ハンカチで拭き2分で遊びに戻った。
- NG:協調性が高い → OK:ルール遊びで順番を守り、2回譲る声かけを自分から行った。
さらに例を増やした完全版は、ハブ記事「児童票の基本」と合わせて運用してください。
5. 個人情報・同意・園内ルール(重要)
- 最小限データのみAIに渡す(匿名化・イニシャル、顔写真や住所は除外)
- 目的外利用の禁止と第三者提供の管理(園のポリシーに明記)
- 保護者への説明:「AIは下書き。最終判断は保育士」を明記
- 保存期間・アクセス権限・退園後のデータ扱いを運用規程に記載
6. よくある質問(AI運用編)
Q. 児童票をすべてAIに任せてもよい?
A. いいえ。AIは下書き支援です。観察と最終判断は保育士が担います。基礎は「児童票の基本」で再確認を。
Q. 表現が固くなります。
A. プロンプトに「保護者に伝わる語彙で」「専門用語は補足」を追加。言い換え辞書で主観→事実に整えます。
Q. 監査対応は?
A. 観察メモと出力の対応ログを保存。修正履歴(版管理)を残してください。
Q. 端末が古いのですが?
A. ブラウザで動くクラウド型なら十分です。まずは軽量な完全無料ツールで挙動をご確認ください。
7. すぐ使えるチェックリスト
- [ ] 観察メモを4観点で記録
- [ ] 年齢別プロンプトで下書き生成
- [ ] NG→OK言い換えで客観化
- [ ] 保護者共有前にダブルチェック
- [ ] ログと版管理を保存
8. まとめ:AIは”時短”だけでなく”質を揃える”補助輪
観察の質を型で揃える → AIで均一の下書き → 人が仕上げ。この流れを定着させると、児童票の説得力と作成効率が同時に上がります。まずは園のフォーマットで試してみてください。

次に読む: 児童票の基本(目的・年齢別の観点・例)

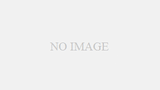

コメント